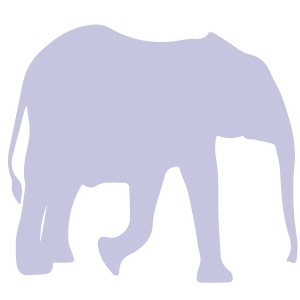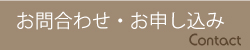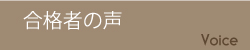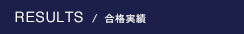RECRUIT/講師採用
講師インタビュー
高石先生(京都大学)
数学と理科、特に生物を担当
蟻と寄生虫の関係について研究中
自身が塾に通ったことが無い
数学と理科、特に生物を担当
蟻と寄生虫の関係について研究中
自身が塾に通ったことが無い
面接当日、履歴書を忘れて
塾に入ったきかっけは?
もともと勉強が得意だったので、勉強を活かせるアルバイトを探していました。
接客業は、その場その場の対応が求められる気がしたので、
自信があった勉強をアルバイトに選びました。
「塾」で働きたかったんですね。
では他の塾ではなく、クレデュにしたのは?
まず、務めるなら個別がよかったんです。
大人数に一方通行の授業をするのはあんまりおもしろくないかなって。
個別塾で、生徒からのフィードバックがその場でもらえる環境のほうがおもしろいかなって思っていました。
また、中高生向けの塾で、特に高校生や大学受験に特化しているところは少ないと思います。
大学1年生の当時、直近で勉強した部分を扱える、高校生向けの授業のほうが自信があったのも理由の1つです。
クレデュは難関大学も目指せる塾なので、講師のレベルに合った生徒を担当できますよね。
実際に講師になってみてどうでしたか?
入塾当初のことについて教えてください。
面接の内容はもう覚えていないんですが、
面接当日に履歴書を忘れて取りに帰ったことは覚えています(笑)
人となりのほうが大事にされていたのかなと思います。
筆記試験は基本的な事柄が聞かれているんだなという印象でした。
自分自身が塾に通った経験がなかったので、
最初は授業がどのようなものかわからなかったので、
他の講師の様子の見学などをして、学んでいました。
ピラミッド構造の枝葉
初の塾デビューの後、4年目を迎えた今、クレデュで働いてみてどうですか?
最初は生徒が分かっているのか、分かっていないのかがよくわからなかったです。
分かっているようで分かっていないことがあったりして。
自分自身も、解き方がわかっていても、ちゃんと伝わるように言語化できていなかったと振り返って思います。
でも数年ぐらい経って、どんどん自分の教え方が固まってきて、
今は思考がシステム化できている気がします。
ちゃんと生徒に伝わっている反応が返ってくると、達成感がありますね。
思考のシステム化、面白いですね。
それについて、もう少し教えてもらえますか?
例えば、数学を教えている場面でも、数Ⅰのこの部分で間違えた生徒が、数Ⅱでもある部分で間違えたりすることがあって。
このことが、階層構造になっていると思うんです。
(ピラミッドの)一番上に目標があって、その目標に向かって枝葉(ピラミッドの最下層)があるイメージで、実生活でもこの構造は使えるなと感じています。
1つの大きな目標を達成するためには、
枝葉の部分が多数存在して、そのどれを選ぶのかという点で、
それぞれのメリットデメリットを考えて選択することになる、ということを表せている気がするので。
なるほど~。日常生活でも最適解を選ぶために、みんながやっていることですね。
数学では、その大きな目標は、例えば大学受験に合格する、ということになると思うんですが、
枝葉はそれぞれの分野の解法、例えば数と式の計算法則がわかるということに当たりますか?
そうです。でも生徒は枝葉しか見えていないんですよね。
本来は大きい目標があって、それを達成するために枝葉は全部同じ目標に向かっていくはずなのに、
生徒は目標のほうが見えていないから、枝葉からスタートして目標から脱線していくのかなと思ったりするようになりました。
数学だったら、こういう全体像があって(数学1A2B全体)、その中の今やっているのはここだよって説明もできると思うんですが、それについてはどうでしょう?
それもやってるんですけど、
生徒にとっては、「なんかすごいことやるうちのここか」くらいで終わって、
枝葉自体を知らないと、そもそも正しく全体像を把握することはできないんだと思っています。
だから目標を知るためにまずは枝葉をそろえないといけない。
でも、枝葉同士の関連性は見えないし、目標も何かわからないままやってるみたいな感じに。
それって英語の文法でも、国語の文法でも言えることですね。
そうだと思います。ここは今も工夫していっているところです。
少し話題を変えて、クレデュならではの様々な取り組みがあると思いますが、それについてはどう思いますか?
授業をいろいろ考えて実践できるのは面白いなって思います。
フィードバックなどの機会があることもありがたいと思っています。
他の塾で働いている同期に聞いても、そんな塾は他にはないんだなと知りました。
他にも、数学科での情報交換、共有の場がありますが、
もう少し頻度を増やせたらいいなと思っているところです。
好きだから、蟻の研究
では最後に、大学での専門について教えてください。
まさにさっきの話で行くと枝葉を実験しているところです。
最終的には、より高次の抽象的な共通点が見つかったら、
学問的に面白いと他の人にも思ってもらえるようになると思うんですが、
まだそれは見つかっていないです。
まだ1年しかやってないので。
学問内容的には、蟻の寄生虫と、例えばキノコと寄生虫の関係とかが同じ点があるというのが見つけられれば、
「共生」というシステムを説明できるかもしれないという感じです。
その対象の規模をどうするかはまだ決まっていないんですが、
とにかく蟻と寄生虫の関係について研究しています。
でも、その共通点があったとしても、
なぜ蟻の寄生虫というところに着目しているのかの説明もしないといけなくなるので、
この辺が今まさに迷っているところです。
学問として世に出すときの難しさですよね(笑)
学問的なあれこれは置いといて、蟻の寄生虫を対象にした純粋な理由は?
好きだから、しかないです(笑)
ただ好きだからこれ(蟻の寄生虫)について扱ってるだけなんですけど、
普通の人はこれ面白いと思わないですよね。
(インタビュアー:私は面白いと思うけど(笑))
将来的にはどうなるんでしょう?
大学の研究職になれたら1番いいんですけど。
でもポストが空いているときに自分が相応の実績があるかもわからないのですぐには難しいですね。
でも一生かかっても研究したいと思っています。
松本先生(京都大学)
数学と理科を担当
半導体について研究中
中学からクレデュに通う大ベテラン
数学と理科を担当
半導体について研究中
中学からクレデュに通う大ベテラン
恩返ししたい気持ち
クレデュに入るきっかけについて、教えてください。
元々中2の時から、クレデュに通っていました。
大学に入って、バイトを探す中で、何か人に教えてみたいという気持ちと、
クレデュに恩返ししたい気持ちがあったため、クレデュに入りました。
恩返し、いいですね!
講師になる際には、面接・筆記試験があったと思うのですが、その内容や研修についてお聞かせください。
面接日は神大の後期日程の試験の日だったことを覚えています。
京大の合格発表が前日あって、合格していたから13時頃に塾に来て面接をしました。
内容は教育に対するスタンスを自分なりにこう思ってますみたいなことを伝え、
それに対して数点コメントがあったような気がします。
そのあと、数学のテストを受け、確率を間違えた記憶があります(笑)悔しかったです(笑)
芯までサポート
松本さんは生徒時代から長い間クレデュと関わりがあると思いますが、
実際に講師になってみて感じたクレデュの特徴はありますか?
まず授業については、集団は1人1人に目が届きにくいから、
個別で教えられるところが魅力の1つだと思います。
クレデュは1:2でも(ブースが区切られていて)1人1人に時間を使うことができるので。
集団は、学ぶためには生徒の積極性(個別に授業後に質問に行くなど)が必要になりますが、
クレデュであれば、他の塾よりも、生徒へのサポートの深さ、ですかね?
深さがあって、芯までサポートをすることができると思います。
自分が集団に通っていた時期もあったので、その部分はより強く感じますね。
授業以外での良いところは、
講師間で企画したり、理系同士で線形代数のゼミをやったりと、
講師同士の交流があるところですかね。
そこで、この(大学の)授業のここがよくわからないという
大学生のあるある話もできたりしました。
クレデュならではの個別対応のきめ細やかさがありますよね。
他にも半期に1度フィードバックの機会があると思いますが、それはどうですか?
1年の経験を総括できる良い機会・修正の機会にもなっていると思います。
受験が終わった後のフィードバックは1年間の受験を見てきた経験を総括できる良い機会です。
受験が佳境になる11月ごろにもフィードバックがあるので、
半年に1回は生徒とのかかわり方を考える上でちょうど良いタイミングだと思っています。
ありがとうございます。
では反対に、クレデュで働いて大変だったことや、
それをどう乗り越えたかについて、何かエピソードがあれば教えてください。
これはクレデュのせいではなくて、個人的な問題なんですが、
大学との距離があり、来るだけで2時間かかることですかね(笑)
ただ、通学中に何か作業や課題などをする時間を作ることで、適応できたと思います。
しんどいときもありますが、最初から高校3年生を持たせてもらったという責任と、
教える楽しさで乗り越えることができました。
(注:クレデュでは講師の実力や成長に合わせて生徒をマッチングしており、初年度から高校3年生を持った講師は歴代で2人しかいません!いきなり受験生を丸投げすることはありませんのでご安心ください)
通学時間が長い講師も多く在籍していますよね。
私も通学時間で過去問の予習をしていた時期がありました(笑)
通学時間中に上手く時間を作る練習ができたことで、
今研究室に所属してたくさんのやることに追われていますが、
時間をつくる面では苦労をしていないですね(笑)
ほめて伸ばすスタイル
現在研究が忙しい時期(卒論の時期でした)だと思いますが、
将来像と今の専門について教えてもらえますか?
今専門でやっているのは半導体についてです。
簡単に言うと、半導体材料で今まで観測されていなかった効果を研究しているという感じです。
ムーアの法則でCPUの性能が上がっていくと言われていますが、限界があるので、
それとは別に磁気を使ったスピントロニクスという新しい方式を使って、
デバイスを作るのが可能になるのではというイメージで基礎研究をしているところです。
beyondCEMOSで調べてみてもらうと、分かりやすいかも。
将来的には一応博士課程まで行く予定です。
大学院に入って修士課程で2年、博士課程で3年、計5年で卒業すると思います。
卒業後はあんまり深く考えていないんですが、
研究にあこがれて大学に入ったので、この5年間で研究をやってみて、
自分に向いていたらそのまま企業でもアカデミアの方にでも残って研究職をする。
向いてない場合は就職するかもしれないですね。
先のことはあんまり心配せずにこの5年、楽しく研究出来たらなと思っています。
研究の道、頑張ってください!
では最後に、教育への想いや楽しさを聞かせてください。
そうですね、なぜできないか、次できるようにするにはどうすべきかを、
生徒にいかに自分で考えるようにするかという、
意識面的なところを毎授業で伝えるようにしています。
今は間違えていても、意識することでできるようになったら良い、という
ほめて伸ばすスタイルです。
上手くハマる子とハマらない子がいるとは思うんですが、
自分はこのスタンスを大事にしています。
もちろん、生徒が置かれている立場を自覚しないといけないときは、
ちゃんと伝えないといけないんですけど、
それ以外の時や、ポジティブな気持ちを持って勉強をしてほしいときは、
あまりネガティブなことを伝えないように工夫しているつもりです。
講師それぞれのスタイルで生徒と向き合っていますよね~。
それでもネガティブなことを言わないといけない場合はどのようにしていますか?
そもそも自分が怒ることができないタイプなので(笑)
結果が悪くても、そこから得られる情報があるからこそ、次を大事にしています。
ゴールは受験でありますが、高校の時の考え方が今後も継承されていくので、
最終的には先の生活に繋がっていくような数学の論理的思考を伝えていけたら良いなと思います。
追加で!授業の後の雑談で、教室長とどのプロテインが良いか相談してたエピソードも載せていいですか?
プライベートの話もしやすい雰囲気ですよね!
大丈夫ですよ(笑)いろんな相談に乗ってもらっていますね。
奥野谷先生(神戸市外国語大学)
英語を担当
春から社会人
在学中にTOEIC 880点を取得
英語を担当
春から社会人
在学中にTOEIC 880点を取得
ガチガチの講師デビュー
まずは、クレデュに入るきっかけについて教えてください。
自分がもともと生徒で、受験が終わった後に
「講師やってみない?」と言う風に言ってもらったのがきっかけです。
声をかけてもらった当時は、自分が第一志望校に落ちてしまったタイミングでもあり、
人に教えるとか人前で話すのが苦手だと思っていたので、その時は断ろうと思っていました。
そのあと、だいぶ迷う時間をもらって、後期で自分がいま通っている大学に合格をもらって。
ちょっと自信がついたのと、誘ってくれた先生が、
「奥野谷さんはこういう良いところがあるから是非やってほしいな」と言ってくださって、
じゃあ自信ないけどやってみようかなって思ったのがきっかけです。
それと、自分が受験生だったときにお世話になった先生に、
恩返ししたいというのも結構大きな理由になっているかな?と思います。
最初はあまり自信がない状態でのチャレンジだったんですね。
では、実際に授業を担当する前の、面接や研修はどうでしたか?
自分が塾生だったのもあって、めちゃくちゃ緊張する感じではなかったですね。
今も覚えているのは、塾の理念とかの説明を聞いたことです。
塾生として通っていた時は、理念について知らなかったんですけど、
そこからぬるっと講師になるのではなくて、ちゃんと説明してくれたのが良かったです。
筆記試験は英語と数学を受けたんですけど、
数学は教える自信がなかったので、のちに断ることができました(笑)
研修のころも自信なかったです。
正直めっちゃ怖かったというか、前日から緊張してました(笑)
そもそも説明するのが苦手だし、アウトプットする機会があんまりないので、
それだけでも緊張するのに、(ロールプレイングで生徒役の)相手は
教えてもらってた先生だったから緊張しました。
悪い意味で真面目なので、最初ロープレするために資料を渡されていて、
これ通りにしないといけないと暗記して、マニュアルを握りしめてやってました(笑)
だから、「そんなガチガチならんでいいよ」と言われた記憶があります(笑)
でも、喝入れられたりすることはなかったです。
そもそも英語が好きだったんですけど、文法が曖昧やったので、
教えるってなったときに文法を一からやり直しました。
それで定着した感じもするので良かったなと思います。
モチベーションが下がっても
ガチガチから始まった講師デビュー(笑)
みんな通る道ですよね。
その後、講師を四年続けたわけですが、実際に働いてみてどうでしたか?
そうですね、生徒と長く信頼関係を築く(年度を跨いで同じ生徒を担当する)というのを
2,3年担当して、大学に合格してという経験を、数年という長いスパンでやってきたので、
そのこと自体が自分の中で自信に繋がったと思います。
それと、学んできたことをアウトプットする場は、
普通に大学生として生活していたら、ないと思うんですけど、
先導型授業をクレデュでしているから、
自分の中で伝えたいことをちゃんと言語化して伝えてあげるということを繰り返して行くうちに、
得意とまではいかないけど、苦手では無くなったかなと思えてて、
成長が自信に繋がったなと思ってます!
だんだんと自信がついてきたら、モチベーションも保ちやすいかと思うんですが、
最初のほうはどのようにモチベーションを維持していましたか?
たしかに、最初のほうとか、3年生のころにモチベーションが下がった時期もありました。
最初は数字で結果が出ないから分かりづらかったです。
大学2年生の時に初めて受験生を持ったので、
そのときがめちゃくちゃやる気に燃えてる時期で、結果も出てみんな頑張ってくれてて良かったけど、
割と次の年に持ってた子がなかなか受験の結果とかも振るわなくて、
1回目ほどの新鮮さがなかったから、ちょっとモチベーション的には低下気味でした。
社員さんに怒られたりするわけではないんですが、
「モチベーションないんですよね…」みたいな感じで相談したりしていました。
社員にモチベがないと言える環境っていうのがいいところですよね〜。
モチベがない時期は、どうやって乗り越えたのでしょうか。
1年のときは受験生を担当していなくて、合格させるという目的がまだなかったし、
経験不足という面もあって、やりがいがあるなと思える域に達していなかったかもしれません。
でも、2年生の時に受験生を持って、もうすでに(1年間担当して)関係がある子やったから
思い入れもあるし、絶対受からせたいっていう気持ちがあって。
なので、やりがいが生まれたのは割とゆっくりめやったかなと思います。
4年やってるので、モチベーション下がったのは何回かありました。
でも、1年生の最初のところで言うと、
自分にとってはいちバイトじゃなくて、ちゃんとほめて評価してくれる人がいることが
その時は1番のモチベーションでした。
もともと尊敬していた大人の人たちがほめてくれたり、こういうとこ良いよねって言う風に
常にフィードバックをもらえたことが大きかったと思います。
なるほど。フィードバックの効果もあったんですね。
そこをもう少し詳しく聞かせてもらえますか?
フィードバックって聞いたら、業務に対してどれだけ成果を出したかを評価されると思われるかもしれないですが、
そうじゃなくて、個人がどんな成長をしたかということに重きを置いてやってくれてるなと感じています。
例えば、私自身だったら、フィードバックの時に毎回課題やんなって言われてたのは、
奥野谷らしさを出して授業して欲しいっていうのを言われてて。
合格何人出せとかそんなんじゃなくって、英語楽しいと思ってるんやったら、
それを相手にも伝えるというか、思考回路を生徒に移してあげてみたいな感じで
アドバイスをくださったのが印象的です。
それから、フィードバックのときも、授業終わりの時間も、
こっちから相談しなくても社員さんから気にかけてくれていたなと思います。
3年生のときに、「将来は教育行きたいんですよ」と言ったら、
「教育だけじゃなくて全部見てから戻るんやったら良いよ」と言われて、
いろいろ見た分いろんな可能性があるんだなと思えて、結果的に良かったです。
講師も学びのある場に
フィードバックは講師としてだけでなく、大学生としても貴重なアドバイスをもらえる時間になっているんですね。
クレデュの強みや魅力は他にはどこにあるんでしょうか?
いっぱいありすぎて何から話したらいいか(笑)
そうですね、いろいろあるんですけど、
例えば、社員の方が、生徒だけじゃなくて、
めっちゃ講師を成長させてあげようと思ってくれてるのが、
こんなにひしひしと伝わってくる塾は、他にはないなと思っています。
生徒の授業方針の話以外も、たくさんコミュニケーションとってくれる方が多くて。
例えば自分の進路の相談とか。
コロナ渦で入学したから、どうしてもコミュニティが狭くなりがちだったんですけど、
そうじゃなくて広い世界があることを掲示してくれる大人が周りにいたことが良かったなと思います。
クレデュは、生徒だけではなくて、講師も学びのある場になっていますよね。
他にも聞かせてもらえますか?
周りの講師がすごく尊敬できる人ばかりなところもすごく刺激になりました。
いろんな分野の人が集まっているので、自分が知らない学問の話を聞けたり。
あと私が1番尊敬しているのは、生徒に向き合う姿勢がめちゃくちゃ真剣な人しかいないことです。
多かれ少なかれ自分自身の受験の成功・失敗体験を持っていて、
それを生徒に受け継いであげようとか、生徒にはこういう思いをしてほしくないという思いを持っている人が多いから、
勉強を教えること自体もそうだし、真剣に進路相談したりしているのを見聞きするので。
熱い思いを持った人が多いと思います。
あと、就活上手くいった理由の1つでもある、
TOEICを全額補助してくれるところもクレデュの良いところだと思います!
「信頼される伴走者」
では今度は奥野谷さんの、生徒とのエピソードや教育への熱い思いを聞かせてください!
えーそうですね(笑)
とにかくクレデュの1:1,1:2の個別指導かつ、
1度生徒を担当すると、ずっとその子が卒業するまで
長期的に信頼関係を築けるスタイルが、私には合っていました。
週に1回しか顔を合わせないので、
担当した最初の方は全然しゃべってくれない子とか、多分ちょっと無理やり塾来させられてるんやろなみたいな子がいるんですけど、
そういう子とかも毎週授業をして、クラブや部活の雑談をずっと積み重ねていくうちに、
心開いてくれて、修学旅行のお土産くれたり、自発的に学校であった面白いこととか話してくれる瞬間があって。
なんか今信頼関係できてるなと思う瞬間がすごく楽しいし、
その積み重ねで受験とかも一緒に頑張ろうと思えるのが好きです。
教えることはこっちから与えないといけないものだと思っていて、
そんな押しつけがましいこと自分がしていいのかと思っていたけど、
実際に教えてみて、上から物を教える必要はないんやなってことに気づきました。
割と授業するときや生徒と関わるときに気を付けてたのは、
自分で「伴走者」って言ってて、威厳ある先生じゃなくてもいいから、
ちょっとだけ前を歩いてるお姉さん的存在になりたくて。
「信頼される伴走者」を目指していました。
自分のキャラ的に人に押し付けたり命令したりすることは好きじゃないから、
横並びではないけど、若干前を歩いて一緒に頑張る「信頼される伴走者」になろうって。
「信頼される伴走者」、素敵ですね。生徒との関係性が伺えます。
では教育に関してはどんな風に考えていますか?
教育に対して、私はあまり公教育、義務教育とかそっちではなくて、習い事の世界とか第三の…。
子供たちにとって、学校でも家でもない場所でずっと教育に関わってきて、
割と教育とか勉強って聞いたら、教えられる側にとっては嫌やなと思うものやと思うけど、
教育ってどっちかがどっちかに一方的に何か教えるものではなくて、
教える側も絶対教えてもらう側と同じかそれ以上に学びあるものだなと思います。
塾で教えてたら、自分は英語が元々好きやってそれを教えるって形でやってるんですけど、
目の前の生徒の子はそんなに英語が好きではない子も結構いるので。
そういった子に教えることによって、
決してその目の前の子って自分と同じ物差しで見てないから、
最初の段階でそれに気づいたことが、今でも印象的ですし、
みんな違う見方をしているという当たり前のことに気づけました。
逆に雑談してくときに、自分と興味の対象とか生き方が違う子たちと関わるから、
自分の世界が広がったんだなって。
教育を受けた子がこれからいろいろ頑張っていくから、教育はめっちゃ大事って感じます。
実際に長い付き合いをして、合格して、
そのあとにわざわざ顔みせに会いに来て、お礼伝えてくれたりとか手紙貰ったりすることがあって。
それがめちゃくちゃ嬉しいし、毎年それがある度に絶対4年間続けようと思います。
あと、見てた生徒の子が実際に後輩の講師として働いてるから、その瞬間が1番嬉しかったかも。
教育への熱い思い、とても伝わりました。ありがとうございます!
「そんなに好きじゃないな」って
では、ご自分の大学ではどんなことを学んでいますか?
また、これからのお話についても聞かせてください。
大学の専攻としては、中国語をずっと4年間朝から行って頑張ってきました。
でも、入学してすぐに、「中国語そんなに好きじゃないな」って気づきました(笑)
英語が好きだったから他の言語もやってみよと思ってやったんですけど、それほどの熱はなくて。
他の授業を聞いたり、バイトをしたり、人とかかわったり。
色んなことをやるうちに、自分とか人間について考える方が好きだなって気づきました。
なので、ゼミは社会心理学に自分で応募して、専攻とは関係ないけど心理学についてやってます。
卒論は「優柔不断」っていう自分と向き合うテーマにしました。
神戸市外大は単科大学ではあるんですけど、別に専攻分野だけをやらなあかんわけじゃないし、
自分の専攻に興味持てなかったら興味の幅を広げて授業を取ったりしてみても良いと思います。
将来についてはとりあえず、春からは全然違う仕事をするんですが、
いつか人生のどこかでは教育に戻ってきたいと思っています。
多分クレデュで働いてなかったら、そうは思わなかっただろうなと思うので、
それくらいやりがいがあったんだなと感じます。
まだできることがあるはずだと思っています。
でも、春からはまだやることよく分かってないんですけど、メーカーでバイヤーをします。
もちろんやる仕事は全然やったことないし、自信もないけど、
でも信頼関係作るとか、そういうところは絶対何かしら活かせることがあると思うから
クレデュの経験を自信にしたいです。
この道を選んだ前提として、大学3年生、4年生と就活を結構頑張ってきました。
最初、教育分野に行こうかなと思った瞬間があって、そっちの道もあったと思うんですけど、
1回は大きいとこ入ってみようって感じで、今の会社を選びました。
最後に、今回のインタビューに向けて語りたいことがいっぱいあってメモまで持ってきてくれた奥野谷さんから、未来の講師になる方へ向けてひとことください!
とにかく、絶対やった方がいい!
やるかめっちゃ迷ってたけど、やってくれてありがとうとその時の自分に思います。
それこそ、コロナで、最初学校に2年くらい行ってなかったから、
バイトしかすることが無くて、クレデュで働いてなかったら多分ダメ人間になってたと思う(笑)
就活を終えた身として思うのは、4年間は長いようで短くて、短いようで長いから、
何か続けようと思うものがないとすぐ終わっちゃう。
私だったらクレデュをそこに選ぶかな。
1個長く続けられる物を持った方が絶対良いと思うし、それがクレデュだったら、私はすごく嬉しいです!
宮﨑先生(同志社大学)
英語と国語を担当
社会福祉全般を勉強中
1回生で留学も経験
英語と国語を担当
社会福祉全般を勉強中
1回生で留学も経験
相手にわかってもらうには
まずはクレデュに入ったきっかけについて教えてください。
生徒の時に入ったきっかけは親が評判良いからっていうので入った感じだったと思います。
講師は、誘って頂いて、こういうバイトしてなかったら勉強しなくなっちゃいそうやなと思ったので入りました。
理由としてはそれが大きいと思います。
そういう環境に置かれないと、勉強しないことを分かっていたので(笑)
あとは長く続けられるバイトが1個あった方が良いかなって思ったので、続けられそうなクレデュを選びました。
生徒も講師も成長し続ける塾がクレデュの特徴ですよね。
入る際には面接があったと思うのですが、面接はどうでしたか?
面接は試される感じではなくて、そんなに重苦しくなかったです。
面接より研修の方が緊張しました(笑)
聞かれた内容は、誘われた後に講師になるか悩んでいたので、
結局なんでこのバイトしようと思ったかを聞かれたりしました。
あとは何の教科を担当したいかも聞かれました。
英語か国語がしたいなーと思っていて、英語は国語ほど得意じゃないけど、
国語を教える方が難しいと言われたので、最初は英語を教えることにしました。
今は英語に加えて国語も教えていますよね。
そこの違いについても伺いたいのですが、
先に面接よりも緊張したという研修についても聞かせてもらえますか?
研修は、最初はめっちゃ緊張したのは覚えているんですけど、英語の文法の授業をやったのが初研修でした。
生徒役が教室長さんで、めっちゃ緊張したんですけど、
人に教えるのって難しいっていうか、
自分が理解していても、相手にもわかってもらうには、今までよりもちゃんと理解してないと難しいなと思いました。
ロープレの時点でそこに気づけたのはすごくいいポイントですね。
実際に教えるときはどのようにその難しさを乗り越えてきたんですか?
マニュアルがめっちゃ便利です。
英文法のテキストは、こうやって書いたら良いかなっていうのが、自分で何回かやって出来たから良いんですけど、
今教えている"木編"(英語長文の塾オリジナルテキスト)とかはめっちゃ参考にしながら授業をしています。
とにかくマニュアルが使いやすいです。
どこを重点的に教えたら良いかっていうのが分かるので、そこをしっかり伝えられると良いかなって。
マニュアルがあると、教える側も心強いですよね。
得意でも、教えるのは難しい
では先ほど少し触れていた、英語と国語を教える上での違いについて教えてもらえますか。
受験生の時は、国語のほうが得意だったんですけど、最近、教えるようになって、教えるのは難しいなと思います。
英語の文法は、何回も何回も伝えるので、今の方が文法が身についてるなっていう感じがあります。
1人1人、生徒によってどこまで言ったら(細かく教えてあげたら)良いのかなっていうのが難しいんですが(笑)
答え合わせをして、うんうんって言ってるけど、意外とわかってないなっていうときは、
そんなに深く(細かい文法まで)言わず、最低限ここだけ覚えてねって感じで教えてます。
ちゃんと合ってるし、なんでこれこの答えにしたんって言ったときに答えれてる子は
より深く細かく教えるようにしてます。
国語は夏から教え始めました。(インタビューは2月に行いました。)
最初は自分も復習しないと、古文の助動詞とか抜けてたから大変やったし、
長文は思わぬところでめっちゃどんぴしゃな答え言われたりとか、全然違うこと言われたりとかしたら、
どう解説に持っていったら良いのか分からなかったです。
今のところ、その子の答えが違う理由を探して、なんでその解き方ではだめかっていうのを言えるようにしてます。
私(インタビュアー)がもともと国語を教えていたので、
教え子の宮崎さんと授業についてあれこれ考えられるようになって、私は感無量です(笑)
他にもいろいろ相談してくれていましたが、今はどんなところが大変だなと感じますか?
本当に国語を教える人ってすごいなって思います(笑)
今の悩みは、高校1年生2年生とは年の差がまだ変わらないから、まだ大丈夫なんですけど、
たまにドキっとする質問をされたりすることはあります。
逆に中1の子とかは難しいです。
教科書通りに説明したら全部さらっと終わっちゃうし、プラスで何か言えることとか無いから、
授業が面白いのかなとか、その子がここに来てプラスになるにはどうしたら良いのかなって。
そこが結構難しいです。
1年目にして、もう授業をただ教えるというところからはみ出して、
「面白い」「プラスになる」ということまで考えられているのがまずすごいと思いますよ!
これからも一緒にいろいろ考えていきましょう。
講師になっても勉強を続ける
では、他の塾と比べて、クレデュの良さは何か感じますか?
同期に、いろいろ評判とか聞いていたら、結構ハードな塾が多そうだなと思います。
責任丸投げとか、しかも知り合いもいない場所でそれは困るというか、自分の性格にはきついなって。
1年生なんですけど、私が同志社やから、同志社の生徒もできるやろみたいな感じで
責任を丸投げされたりすることはないので、そこは安心して、
今の自分の実力に合った生徒と組み合わせてもらっていると思います。
困ったとしても、クレデュはどうしたら良いですかってすぐ聞ける先輩もいるし、
その辺は手厚いなと思います。
あと、他の塾はとにかく夏期、冬期の講習を自分の希望のシフトの倍くらい入れられるとか、
高3の子をいきなり任されて荷が重いとか、悩んでいてもどうしたら良いか聞けないとか、
そういう話を結構聞きます。
クレデュはそのあたりが全くないので。
特に授業終わりにはよく先輩に相談していて、それが自然とできているのがいいなと思います。
クレデュは講師と生徒のマッチングをちょうどよい具合にしてくれていますよね。
他にも、クレデュで働いてよかったと思うことはありますか?
生徒の子がプライベートな話とかをしてくれるときが嬉しいなと思います。
「来月誰かのライブ行くんですよ」みたいな話を楽しそうにしてくれたら良いなって。
こっちまで楽しくなります。
それから、さっきと被るんですけど、
教えるには今まで学んでた時よりも勉強しないといけないし、自分がわかっていないといけない。
教科書に書いてることよりもちゃんと理解しとかないと、
聞かれたときに困るなっていうのを感じます。
関係代名詞の時に不定詞を間違えてて、不定詞も説明しないとあかんっていうときに、
ちゃんと不定詞のことが頭に入っとかないといけないし、
そこは今までよりも勉強しなあかんし、覚えとかなあかんと思いました。
なので、講師になっても勉強し続けられています。
1年目がちょうど終わる時期の今の、宮崎さんのインタビューは、
特にこれから講師になる方々に響いていると思います!
この学科でよかったなと思う
最後に、現在学んでいることや将来像について教えてください。
今、私は社会福祉学科で学んでいて、1年生なので社会福祉全般の概要を知る授業が多いです。
今までの自分の人生では、出会ったことのない人たち(貧困の人たちなど)が、
実際にいることは知っていたけど、これまでには見えていなかった人たちについて知ることができています。
それと、実際に年取ったときの年金問題とか、認知症とか、
全然自分が経験するかもしれないことについて勉強してるのが、
面白いっていうのは、違うかもしれないんですけど、この学科で良かったなと思っています。
もともと社会福祉学科を選んだのは、
そんな「これを学びたい」っていう学問がなかったから、広く学べるところやったらなんでも良いかなっていうのと、
おばさんが老人ホームで働いてて、小さい時によく遊びに行ってたんですけど、
おもしろいし社会福祉やってみたらって言われて、
そんなに他の学問に対して強い意思があるわけでもなかったから受けてみました。
結果、今面白いと思っているので、合っていたんだなって思っています。
家族が結構、みんな福祉系なので、将来は私だけは普通に就職してやるっていう謎の意地があって(笑)
安定した企業に入るか、公務員になるかのどっちかかなぁと今は思っています。
本が好きだから、出版系も良いかなって思うんですけど、出版って将来大丈夫なのかなとか不安で。
好きを仕事にするなら出版系、そうじゃないなら公務員とか企業とか安定を選びたいかなと漠然と考えているところです。